休診:土曜16-19時・日曜・祝日
肝胆膵腎疾患
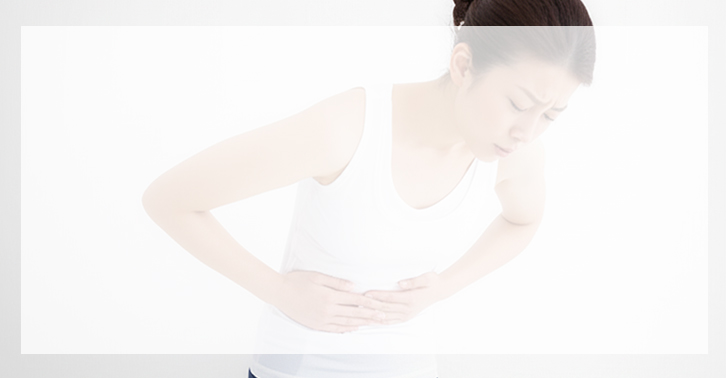
腹部超音波検査とは?
腹部超音波検査(腹部エコー)は、体の外から超音波(高周波の音波)をあてて、腹部内の臓器の様子をリアルタイムで観察する検査です。放射線を使用しないため、体への負担が少なく、痛みもありません。ご高齢の方にも安心して受けていただける検査です。
検査でわかること
この検査では、以下の臓器の状態を確認できます:
• 肝臓(脂肪肝、肝硬変、腫瘍など)
• 胆嚢(胆石、ポリープ、炎症など)
• 膵臓(膵炎、腫瘍など)
• 腎臓(結石、嚢胞、腫瘍など)
• 脾臓
• 大動脈(腹部大動脈瘤など)
• その他、腹水や腫瘤の有無など
超音波検査の最大のメリットは、放射線被ばくもなく、ほぼ無侵襲な検査であるということです。一定時間絶食の状態であれば検査可能なので、当院では上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を受けにいらした方には、一応超音波検査も提案させていただいております。過去には全く無症状でありながら、胆嚢癌・腎癌・膀胱癌などが見つかって早期治療に繋がったり、原発不明の肝転移が見つかって基幹病院に紹介したこともあります。
また一方、検査担当者の技能や情熱、検査機器の性能によりかなり診断能が左右されるのも事実です。ドックなどで超音波検査を受けられた方も、特に脂肪肝のフォローには客観的に数値化して評価できる機能も備わっていますので、検査をお勧めします。
主な肝臓疾患について
次に、主な各臓器の疾患について説明します。
肝臓は、体内で次のような重要な役割を担っています。
• 栄養素の代謝(糖質・脂質・タンパク質の変換)
• アルコールや薬、老廃物の解毒
• 胆汁の生成(脂肪の消化に必要)
• 体内に必要なタンパク質の合成
• ビタミンや鉄分の貯蔵
これらの機能がうまく働かなくなると、全身にさまざまな不調が現れることがあります。肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、自覚症状が出にくいまま病気が進行することが多い臓器です。
①脂肪性肝疾患(脂肪肝)
近年、非常に注目されております。
脂肪性肝疾患とは、肝臓に過剰な脂肪が蓄積した状態を指し、現代の食生活・生活習慣と深く関係があります。
•NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)
アルコールをほとんど飲まないのに脂肪肝になる状態。生活習慣病(肥満・糖尿病・高脂血症など)との関係が深く、日本人の約3人に1人が該当するといわれます。
•NASH(非アルコール性脂肪肝炎)
NAFLDの一部が進行した状態で、肝臓に炎症や線維化が起こり、肝硬変や肝癌につながることもあります。
以下の項目に当てはまる方は、脂肪肝のリスクが高いといえます:
• BMIが25以上(肥満)
• 内臓脂肪型体型(お腹周りが気になる)
• 糖尿病・高血圧・脂質異常症がある
• 食生活が不規則、野菜不足、間食が多い
• アルコールは控えているのに肝機能異常を指摘された
• 健康診断で「AST/ALT」や「γ-GTP」が高い
初期にはほとんど自覚症状がありませんが、放置すれば肝硬変や肝細胞癌のような深刻な疾患に進展する恐れがありますので、上記に該当する方は定期的超音波検査をお勧めします。当院の超音波検査は、脂肪肝を定量的に評価できる機能(ATI medium)が備わっております。
②慢性肝炎(B型・C型ウイルス性肝炎など)
肝炎ウイルスが長期間にわたり肝臓に炎症を起こす病気です。
進行すると肝硬変・肝癌のリスクが高まりますが、現在では有効な抗ウイルス薬が開発され、早期に発見されればほぼ治る疾患と言えます。
③肝硬変(かんこうへん)
慢性的な肝障害が進行し、肝臓が硬く変性してしまう状態です。
腹水、黄疸、出血傾向、意識障害など重い症状が出ることもあり、命にかかわる合併症のリスクがあります。
④肝細胞癌
日本ではC型肝炎などの慢性肝疾患から進行することが多く、定期的な画像検査での早期発見が生存率を左右します。
初期には自覚症状がほとんどありません。
胆嚢・胆管系の疾患について
胆嚢(たんのう)や胆管(たんかん)は、肝臓で作られた胆汁を貯めたり、十二指腸へ送る重要な役割を果たしている臓器です。これらの器官に異常があると、日常生活に支障をきたすだけでなく、重篤な病気に進行することもあります。
•胆石症(たんせきしょう)
胆嚢や胆管内に結石(石)ができる病気で、右上腹部の痛みや吐き気、発熱などの症状を伴います。無症状の場合もあり、健康診断などで偶然見つかることもあります。
•胆嚢ポリープ
胆嚢の内壁にできる突起状の病変で、多くは良性ですが、大きさや増大傾向によっては癌化の可能性もあるため、経過観察が必要です。
•胆嚢炎・胆管炎
胆石や細菌感染により炎症が起きる病気で、強い腹痛や発熱、黄疸(おうだん)などを引き起こします。早急な治療が求められます。
•胆嚢癌・胆管癌
膵癌と同様、進行するまで症状が出にくく、発見が遅れやすい悪性腫瘍です。胆管の拡張など、少しでも疑わしい所見があれば、精査目的に基幹病院へ紹介いたします。
膵臓の疾患について
膵臓(すいぞう)は、胃の後ろ側に位置する臓器で、消化酵素や血糖値を調節するホルモン(インスリンなど)を分泌する重要な役割を持っています。
①膵炎
膵炎には、急性と慢性の2つのタイプがあります。
急性膵炎(きゅうせいすいえん)
膵臓が突発的に強い炎症を起こす病気で、次のような症状が見られます。
• 激しい上腹部の痛み(背中まで響くことも)
• 吐き気や嘔吐
• 発熱、腹部膨満感
原因として多いのは:
• 飲酒(特に大量飲酒)
• 胆石
• 脂っこい食事
• 一部の薬剤やウイルス感染 など
放置すると膵臓の組織が壊死したり、全身状態が悪化することもあり、早期の診断と治療が非常に重要です。
慢性膵炎
膵臓に慢性的な炎症が続き、徐々に膵臓の組織が破壊されていく病気です。
初期は無症状のこともありますが、進行すると以下の症状が現れます。
• 持続的な腹部や背中の痛み
• 体重減少
• 下痢・脂肪便(脂っぽい便)
• 血糖値の上昇(糖尿病の原因にも)
慢性膵炎が長期間続くと、膵癌のリスクも高まるため、早期の診断と生活習慣の見直しが必要です。
②膵癌
膵臓はお腹の奥深くに位置しており、初期にはほとんど症状がないため、膵癌は非常に早期発見が難しく、見つかった時には進行していることも少なくありません。
一方で、**「膵嚢胞(すいのうほう)」や「IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)」**といった比較的初期の病変を見つけることで、膵癌のリスクを早期に評価し、将来的な癌の発症を予防することができます。
近年、多くの医療機関で「膵癌早期発見プロジェクト」を展開しており、胆道系同様、当院でも疑わしい所見が少しでもあれば、連携する基幹病院へ精査目的に紹介いたします。
③膵嚢胞・IPMN
◇ 膵嚢胞とは?
膵臓に液体がたまった袋状の構造(嚢胞)ができる状態です。多くは良性ですが、なかには将来的に癌化する可能性のあるタイプもあります。
◇ IPMNとは?
IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)は、膵管の中に粘液を分泌する腫瘍で、膵癌の前段階とされる病変です。大きさや位置によって「主膵管型」「分枝膵管型」に分類され、適切な経過観察や治療が必要になります。
代表的な泌尿器疾患
①腎癌(腎細胞癌)
腎臓にできる悪性腫瘍です。初期は無症状ですが、進行すると以下のような症状が現れることがあります:
• 側腹部や腰の痛み
• 血尿(目に見える場合もあれば、検査で見つかることも)
• 腹部のしこり
• 倦怠感・体重減少
腎癌は早期発見で治療成績が大きく変わります。
②腎嚢胞(じんのうほう)
腎臓の中にできる液体の袋で、多くは良性です。自覚症状はなく、健康診断などで偶然見つかることがほとんどです。
ただし、嚢胞が大きくなったり、多数できる場合(多発性嚢胞腎など)には注意が必要です。年1回程度の経過観察をおすすめしています。
③膀胱癌
膀胱の粘膜にできるがんで、50歳以降の男性に多く、喫煙が大きなリスク因子です。
主な症状は:
• 血尿(痛みを伴わないことが多い)
• 頻尿や排尿時の違和感
• 尿が濁る、臭う
特に**「痛みのない血尿」**は膀胱癌の典型的なサインですので、見逃さないことが大切です。

